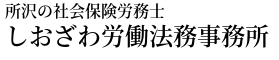懲戒処分の前に ~留意点と実務対応~
経営の都合上、懲戒処分を検討せざるを得ないケースが生じることがあります。
懲戒処分は企業秩序違反への特別な制裁措置とされ、主な処分に「けん責・戒告」「減給」「降格」「出勤停止」「懲戒解雇(諭旨退職、諭旨解雇)」があります。
これらの処分は従業員にとって重大な不利益となるため、労働契約法に特に定めがあり、処分の際には、懲戒権の濫用として無効とされないか、考慮する必要があります(労働契約法15条)。
以下、労働契約法の定めに沿って、懲戒処分を有効とする条件を1.~3.にとりまとめました。また4.では、実務的な対応と留意点についてご紹介します。
1.根拠規定があること
まず大前提として、懲戒の理由となる事実(事由)とその事由に応じた懲戒の種類と程度が就業規則に明記されていなければなりません。また、この懲戒規定は、規定される前の事案には適用されず、1回の事案に対して2回以上処分を行ってはならないとされます。
2.懲戒事由に該当し客観的に合理的な理由があること
つぎに、事案の内容が就業規則の懲戒事由に該当していて、懲戒処分に客観的にみて合理的な理由がなければなりません。
裁判所はこの判断にあたっては、労働者の保護を目的に、就業規則を文字通り解釈せず、具体的、限定的に読み取る傾向があります。
たとえ就業規則にのっとった懲戒処分であっても、具体的な内容によっては無効とされることがあります。
3.懲戒処分が社会通念上相当なものであること
また懲戒処分は、その「行為の性質・態様その他の事情に照らして社会通念上相当なものと認められない場合」には無効とされます。
情状酌量が不十分で量刑が重すぎるとされるケースや、同じ様な過去の事案への処分と比べて重すぎるとされるケースなどがこれにあたります。
このほか、懲戒の手続きが社会通念上、相当であることも求められています。
就業規則等に規定された懲戒委員会の討議などの手続きを守ることはもちろん、規定がない場合も、本人に弁明の機会を与える必要があるとされています(以上、菅野和夫「労働法」参照)。
4.懲戒処分前の実務対応
「事実関係の把握」
もし懲戒事案が発生したときは、ただちに本人や関係者から事実関係を聴き取り、事実関係を把握します。
必要に応じ、本人を自宅待機とする対応も考えられます(懲戒処分の「出勤停止」とは異なります。賃金を支払わない自宅待機については別途検討が必要です)。
「通常の措置での対応も」
事実関係と就業規則の定め、社内の過去の事例や労働判例を判断材料として、懲戒処分とすべきかどうか、量刑はどうするか、検討します。
グレーな事案や、情状酌量の余地のある事案では、ひとまず通常の労務管理の手法で対応することも検討してください。
業務上の注意や指導、警告、配置転換などが考えられます。
雇用継続が困難と考えられる事案であれば、合意退職の勧奨や普通解雇も検討の余地があります。
「懲戒解雇に解雇予告・解雇予告手当が必要か」
事案によっては、懲戒処分のうち最も重い、懲戒解雇を検討せざるを得ないことがあります。懲戒解雇イコール即時解雇で、解雇予告は不要と誤解されることもありますが、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇予告または解雇予告手当の支払は必要です。
労働基準法により、事業主が労働者を解雇するときは、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(平均賃金を何日分か支払う場合、その分予告期間を短縮できます。)。
なお、解雇予告手当には遡及支払は認められません。
即時解雇するときは通知と同時に、予告と予告手当の支払を併用するときは解雇の日までに支払うこととされています。
「労基署の解雇予告除外認定」
原則として事前に事業主が労基署に申請し、認定を受ける必要があるとされています。
労基署は申請を受け、「重大な服務規律違反または背信行為があったか」当事者双方から直接事情を確認して判断します(労働者保護の観点から、認定には大変慎重です)。認定されないときは、懲戒解雇とあわせて解雇予告をするか、解雇予告手当を支払う必要があります。
認定より先に懲戒解雇する場合は、事後に認定されない場合があることも念頭におき、対応されることをお勧めします(認定は懲戒解雇そのものの有効性を判断するものではないため、後々解雇の無効を主張される可能性もあります)。